日本で「丈夫で長持ちする」家の条件はは3つ。
地震、白アリ、湿気、これまでもお伝えした通りです。
そのうちの一つ目は、地震に強いこと。
ではどうすれば良いのか?
耐震等級、構造計算書、地盤調査、地盤改良、、、様々ありますが、
今回は耐震等級についてお話しします。
耐震等級とは国が定める建築基準法でどの位の地震に対して
建物が倒壊しないかという基準になります。
耐震等級 1 は建築基準法で定める最低基準で、
100年に一度の地震が来ても倒壊しない強度ということです。
これをクリヤーしないと確認申請が許可に成らず、住宅の建築はできません。
耐震等級 1 は、あくまでも最低基準です。
耐震等級 1 の1.25倍が耐震等級 2 になります。
さらにこの耐震等級 2 の1.25 倍が耐震等級 3 になります。
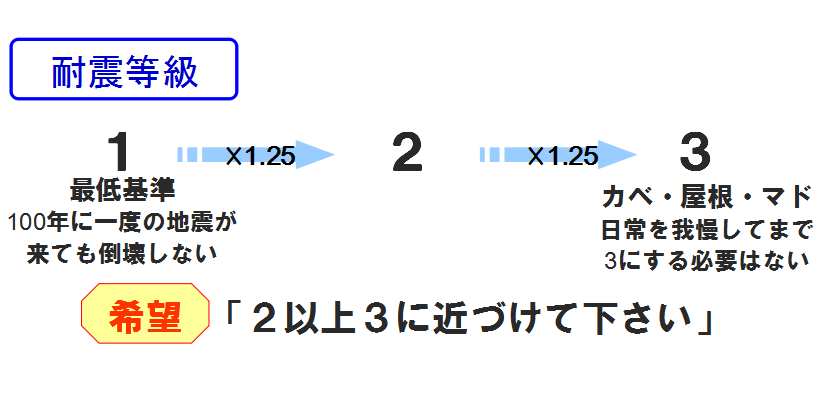 となると、、、やっぱり耐震等級 3 でないとだめだ !
、、、とはなりません。
耐震等級 3 の場合は、壁の多さや屋根・屋根など、日常の生活にも
制限が掛かるような我慢を強いられることになってしまいます。
例えば、南側の窓は大きく取れずに小さくするしか仕方がありません。
これでは明るく開放感のある室内にはなりません。
そこまで我慢して耐震等級 3 を確保する必要はないと私は考えています。
耐震等級 2 以上かつ 3 に近付ける方法が最良と考えます。
では、どうすればいいのか、、、。
プラス α の構造・耐震対策を行います。
私がお薦めするのは、伝統工法と制震ダンパーなどの柔構造的な
考え方の耐震補強です。
特に伝統工法の長ほぞ込み栓工法などは、
理に適った方法で昔から京都や奈良の寺社建築で用いられて来た、
地震に強い構造補強方法です。
ただ残念ながら、現在の国が定める建築基準法では、
そのままでは構造補強方法と認められておりません。
個別の大変手間の掛かる方法を用いなければならないので
広く使われることが少なくなっています。
残念ですが、、、。
しかし、、、このことがプラス α の耐震になることは間違いありません。
制震ダンパーも揺れの力を摩擦や油圧の熱エネルギーで吸収して
地震の揺れを緩和させ有効です。
このような対策で、地震強い丈夫で長持ちする
耐震等級 2 以上、3 に近付き、3 以上とも言える耐震強度が確保できる訳です。
耐震等級は、2 以上、3 に近づける!
これを実践してください。お願いします。
私たちがグランフロント大阪で開催する
「家づくり計画セミナー」では、このようなこともお話ししています。
生涯で一番大きな買い物「家・住宅」ですから自分自身でしっかり勉強して、
絶対に失敗しない「家づくり・住宅購入」をしなければなりません。
お気軽にご参加ください。
となると、、、やっぱり耐震等級 3 でないとだめだ !
、、、とはなりません。
耐震等級 3 の場合は、壁の多さや屋根・屋根など、日常の生活にも
制限が掛かるような我慢を強いられることになってしまいます。
例えば、南側の窓は大きく取れずに小さくするしか仕方がありません。
これでは明るく開放感のある室内にはなりません。
そこまで我慢して耐震等級 3 を確保する必要はないと私は考えています。
耐震等級 2 以上かつ 3 に近付ける方法が最良と考えます。
では、どうすればいいのか、、、。
プラス α の構造・耐震対策を行います。
私がお薦めするのは、伝統工法と制震ダンパーなどの柔構造的な
考え方の耐震補強です。
特に伝統工法の長ほぞ込み栓工法などは、
理に適った方法で昔から京都や奈良の寺社建築で用いられて来た、
地震に強い構造補強方法です。
ただ残念ながら、現在の国が定める建築基準法では、
そのままでは構造補強方法と認められておりません。
個別の大変手間の掛かる方法を用いなければならないので
広く使われることが少なくなっています。
残念ですが、、、。
しかし、、、このことがプラス α の耐震になることは間違いありません。
制震ダンパーも揺れの力を摩擦や油圧の熱エネルギーで吸収して
地震の揺れを緩和させ有効です。
このような対策で、地震強い丈夫で長持ちする
耐震等級 2 以上、3 に近付き、3 以上とも言える耐震強度が確保できる訳です。
耐震等級は、2 以上、3 に近づける!
これを実践してください。お願いします。
私たちがグランフロント大阪で開催する
「家づくり計画セミナー」では、このようなこともお話ししています。
生涯で一番大きな買い物「家・住宅」ですから自分自身でしっかり勉強して、
絶対に失敗しない「家づくり・住宅購入」をしなければなりません。
お気軽にご参加ください。
 地震に強く、心地よい家って・・・?
↓ ↓ ↓
【7/23(土)残2席】グランフロント大阪開催 「家づくり計画」セミナー
↓↓ 詳しくはこちらのイベントページをご覧ください ↓↓
地震に強く、心地よい家って・・・?
↓ ↓ ↓
【7/23(土)残2席】グランフロント大阪開催 「家づくり計画」セミナー
↓↓ 詳しくはこちらのイベントページをご覧ください ↓↓
![]() ]]>
]]>